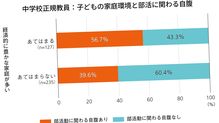※本稿は、早野元詞『エイジング革命 250歳まで人が生きる日』(朝日新書)の一部を再編集したものです。

成人に必要な睡眠時間は7~9時間
老化を抑制する実学について、簡単におさらいしましょう。
・日々の生活習慣は、DNAの情報である“遺伝子の使い方を決める”エピジェネティクスとして、人体に記憶されていく。
・こうしたエピジェネティックな変化を調べることで、ヒトのエイジング・クロック(生物学的年齢)を測ること(=老化の測定)が可能である。
・BMIや血糖値、睡眠などが悪化すれば、老化の客観的指標であるエイジング・クロックが加速したり、エイジング・ホールマークス(老化の特徴)が生じて老化が進む。
こうした老化を制御する指針について、さらに見ていきたいと思います。
まずは、老化抑制に効果的な日頃の習慣から始めましょう。
全米睡眠財団(NSF/National Sleep Foundation)によれば、成人の一晩当たりの必要な睡眠時間は7〜9時間です。それにもかかわらず、65歳以上の高齢者の総睡眠時間は、一晩当たり通常6.5〜7時間程度です。
ちなみに、私自身の平均睡眠時間は5時間弱です。徹夜明けの昼食後はたまに眠くなりますが、夜はコーヒーを飲んだ直後でも入眠まで一瞬なので、さほど不便は感じていません。ただし、就寝直前までブルーライト満載のパソコンと照明の下にいると、寝つくのに時間がかかりますし、睡眠の質も悪くなるようです。
睡眠には男女差がある
睡眠には、レム(REM/Rapid Eye Movement)睡眠と、ノンレム(non-REM)睡眠があります。双方を交互に繰り返しながら、記憶の形成や、脳内から代謝産物を排除するといったさまざまな働きをしています。眠らせないことが拷問の一つの手段であることからもわかるように、最悪の場合、眠りの欠乏が死へとつながることもある。いわば、食事よりも緊急性を要する大切な機能であるのが睡眠です。
実際に睡眠障害は、認知症やうつ病、糖尿病といった疾患の発症リスクになります。さらに、加齢に影響を受けやすいのも大きな特徴の一つです。睡眠の質や効率の低下、睡眠の断片化、日中の眠気、もしくは小さな物音でも起きてしまうなど、大なり小なりの睡眠障害は加齢に伴い増えていきます。
睡眠は、男女の性差が顕著に見られます。37歳から92歳までの2500人以上を対象にした調査では、ノンレム睡眠のうち、脳波の周波数が低い「徐波睡眠」に違いが見られました。70歳以上の男性では、55歳以下の男性に比べて徐波睡眠が50%も減少しています。また、女性に比べて男性のほうが3倍も徐波睡眠不足に陥ることがわかりました。
つまり、加齢ばかりでなく性差も、睡眠の質に影響を与えることが示されているのです。実際、徐波睡眠の減少が認知症の危険因子である可能性も科学的に報告されています。